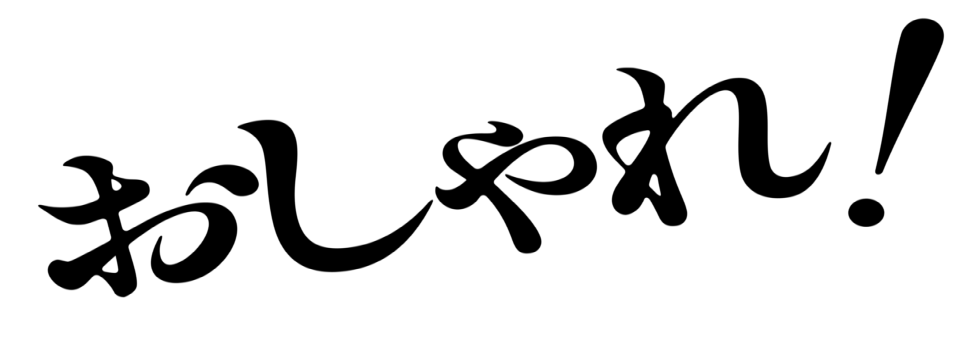おしゃれSHOP Blog
2023/04/11 08:55
おしゃにちは!
店主が最近、友人の伊藤さんという人のすすめで読んだこの本

とてもとても良くてめっちゃ刺激になりまんた😭
日本に初めて雑貨店とゆう概念を作ったといわれる
「文化屋雑貨店」の創業者長谷川義太郎氏によるものです。
長谷川氏はサラリーマンデザイナーを3年やって
なんか違うなと思って退職
自分の買いたいものが店に並んでないので
1972年に作ったのが文化屋雑貨店。
元々の生家は東京下町にある医院で
その医院を閉業するときに、什器や備品
パイプベッドをリペイントしたり
レントゲン写真などを友人に売ったりしたら
不気味で逆に面白いと評判になり
その時の経験が雑貨店経営に繋がったそうです。
人体模型などの病院モチーフがキモかわいいとサブカル的に人気に出たりしましたがその視点を作ったのは長谷川氏だったのですね。
時は高度成長期
日本は戦後の焼け跡から復興し
大量のモノが店先に並びはじめた時代でしたが
大量生産品には面白みもなく美的センスも刺激されず
満足できなかったという長谷川氏
もう古い!と人が見向きもしなかった
ブリキのおもちゃや
プリントのずれたチープな香港雑貨
きいちのぬりえなど
これは!と思うものをお店に並べ
「キッチュ」というジャンルを生み出します。

↑このダサイ人も進んだ人もどちらも困るって表現すごい良いですね、、チャキチャキの下町っ子なので、こんな小気味の良い江戸っ子口調で本が進んでいって面白い🤗
長谷川氏のモットーは
「売れるものより売りたいものを!」
文化屋雑貨店が、その時々で取り扱っているものがまったく違ったのは
ヒット商品になったら
取り扱うのをやめてしまうから。
「だって売れるって分かってるものを売ったって面白くないでしょ」
というのが長谷川氏の弁で、
うわーっ!と声を出してしまうほど共感しました。
これはお店やりながら私も感じてたことだったんです。
まだ1年にも満たない小さな小さな駆け出し🔰のお店ですが
売れ筋とか、これは反響ありそうとかは
見えてきます。
今で言うと、、平成レトロ、ファンシーなもの、とかですか、
でも売れるとわかってる売れ筋を仕入れてきて並べて売るって、
それはただ右から左に商品を移動させてるだけでは?
安く買った株を、高くなった時に売るみたいなマネーゲームみたいというか、、そんな気持ちを抱えてました。
悪くいうと、転売屋、せどり、
そういう人たちとどう違うのかと😞
誰かの作り出したブームにのっかって
ブームを消費して、飽きられて、
食いつぶして、ハイさようならでペンペン草も残らない、
そんなことがやりたいかというと
そうでは無いんです、勿論です
そこにはやっぱり何か
新しい視点の提供、新しい価値の提案
そういうものが無いと
お客様にも私にもときめきがありません。
長谷川氏は雑貨を通して
「ライフスタイルを提案する」
今では至極当たり前になったことを初めてやった人です。
雑貨屋は若い女性や主婦のあこがれの仕事になり
地方ならともかく
東京にはハイセンスでステキな雑貨店は
掃いて捨てるほど
大量にあります。
その中でお客様に支持されるオンリーワンの存在感を放つお店になるのは
本当に難しいことだと思います。
冒頭に出てきた、この本を勧めてくれた伊藤さんがやっている中野ロープウェイというお店にはそのオンリーワンの存在感があり
やはりそこには「売りたいもの」が明確だということ
それまで見向きもされなかったようなチープでキッチュな雑貨をかわいいものとして見る、新たな視点の提供があったのだと思います。
はてさて、、
このおしやショはこの先どうなるのか、、笑
悩まない日はありません。
どんな店にしていきたいのか?
売りたいものは何か??
そこをあいまいにせず
いつも問い続けたいと思っています。
それとこの本はかつて文化屋雑貨店が扱っていた雑貨の写真も沢山で懐かしくて楽しいです。
仕入先の全国各地の問屋さんとの縁、会話も面白い!
やっぱり商売の本質って「人との繋がり」だな…と思います。
人間を人間たらしめてる要素でもあります。
仕入れは全部ネットでも完結してしまう時代ですが
やっぱりそれでは物足りない、なるべく頼りたくありません
対面でないと築けないコミュニケーションがあります
お客さまのみならず、仕入先でで出会った人たちとの縁は大事にしたいとわたしも思いました、、😢
本当にオススメの本です❣️